
Q2 耐震診断や耐震補強に関する自治体の取組みは、どうなっているのでしょうか?
Q3 地震保険とは、どのような保険ですか?仕組みを教えてください。
Q4 耐震構造と免震・制震構造とは、どのように違うのですか?
Q5 リフォームで耐震補強するときに、制震部材を使って補強しても大丈夫でしょうか?
Q6 1981年6月以降に建てられた住宅なら安心なのでしょうか?
Q7 木造住宅は、鉄筋コンクリート造などに比べると地震に弱いのですか?
出所:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合著、書籍「地震でも安心な家」より
耐震工事にかかる工事費用は、補強箇所や補強内容などによってかなりの差があります。一般的には、少ない費用で最大の効果が出る補強工事が理想です。
木耐協(日本木造住宅耐震補強事業者協同組合)が実際に行った耐震補強の工事費用(下図左グラフ)とアンケート調査(下図グラフ)による希望費用を紹介します。
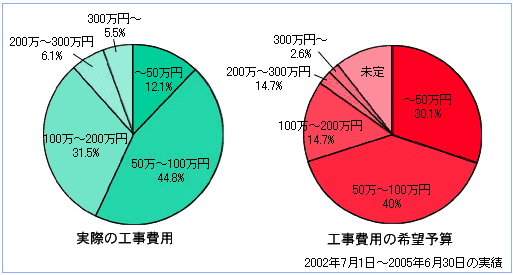
補強プランというものはパッケージ化できるようなものでなく、1棟1棟検証が必要です。
また、耐震補強工事はリフォームを行う際に同時に実施するのが効率的です。耐震補強工事の費用は、おおむね「解体費用:1・補強費用:6・復旧費用:3」ですので、リフォームと同時に補強を行うことでそのコストは約半分ぐらいに抑えることができます。いつくるかわからない地震だけに費用をかけるのは難しくとも、せっかくリフォームするのだから同時に耐震性も担保するというのは非常に合理的ではないでしょうか。
阪神・淡路大震災後に施行された「耐震改修促進法」を受けて、耐震診断・耐震補強に対する融資制度や補助制度を設ける自治体が増えています。耐震改修促進法は、学校、病院、百貨店、ホテルなど多数の者が利用する3階建て以上、1,000平方メートル以上の建築物を対象に耐震診断や耐震改修を行うことを定めた法律(1995年12月施行)ですが、多くの都道府県や市区町村では、一般の木造住宅を対象に耐震診断や耐震改修への補助金交付、融資斡旋、診断技術者の派遣などさまざまな奨励策を実施し、地震に対する住宅被害の軽減に取り組んでいます。
2005年度には、政府は「住宅・建築物耐震改修等事業」として戸建て住宅やマンションを対象に補助金の交付を盛り込んでいます。以下の表は横浜市の事例です。
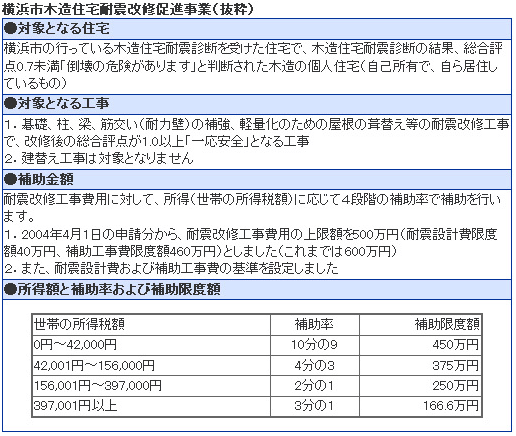
出所:横浜市Webサイト
多くの自治体が耐震診断や補強に対する補助金や融資制度などを創設していますが、耐震診断の経験が少ない技術者が派遣されてきたり、制度そのものが使いにくかったり、一部の団体の既得権的に運用されているなど、診断しても補強が進まないという現実があるようです。皆様にとって使いやすく、耐震補強に積極的な事業者が使いやすい制度に改良することで、もっと多くの方がリフォームを実施する際に事業者から耐震補強を提案され、補助金が受けやすくなるのではないかと考えます。
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバッ,クアップしています。
補償内容
地震保険では、地震、噴火、津波で建物や家財が次のような被害を蒙った場合に保険金を支払います。
1)地震により火災(延焼を含む)が発生し、家が焼失した。
2)地震により家が倒壊した。
3)噴火により家が損壊した。
4)津波により家が流された。
5)地震により家が埋没した(火災保険+地震保険)。
地震保険の契約
地震保険は単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要があります。
火災保険の契約期間の途中でも地震保険の契約ができます。地震保険は建物と家財のそれぞれで契約します。
契約金額は、火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内です。なお、建物は5.000万円、家財は1.000万円が契約の限度額になります。
戸建て住宅の地震対策には、大きく分けて次の3つの方法があります。
1)耐震構造
2)免震構造
3)制震構造
耐震構造とは、土台や柱、梁など建物の構造体を強くすることによって地震に対抗するものです。
筋交いを入れた耐力積にしたり、土合と柱をホールダウン金物でしっかりと補強するなどして建物の耐震性能
を高め、地震で建物が揺れても被害を少なくすることができます。
しかし、耐震性能が不十分であると、大きな地震に遭遇したときに建物に被害を受けたり、家具の転倒や移動が生じることがあり、地震直後の建物の機能を確保できないこともあります。建築基準法では、中地震(震度5強程度)や大地震(震度6強以上)に対しての耐震基準を設けていますが、それは、中地震に遭遇したときに建物の構造体に部分的なひび割れなどの損傷が生じても、修理すれば住み続けることができる水準です。また、阪神・淡路大震災のような大地震に対しては、建物の修復が困難なほど壊れても、倒壊までは至らない程度の水準ということです。
つまり、建築基準法は、耐震性能の最低基準を満たすことを義務づけているもので、決して絶対的な安全を保証しているわけではないのです。
そこで、耐震性能をよくして大地震に遭遇しても、”もっと安全な家”にしようというのが、免震構造や制震
構造の考え方です。
免震構造とは、地震の揺れがそのまま建物に伝わらないような免震装置を建物と基礎の間にはさみ込んで、地震力の侵入を低減する仕組みです。
一方、制震構造は、地震エネルギーの吸収を建物の構造体自体で行わずに、建物内に設置した「ダンパー」と
呼ばれる特殊な装置で行う仕組みです。
住宅の耐震補強では「耐震」が最も一般的ですが、最近は「免震」や「制震」といった技術もどんどん出てきています。「免震」の構造にするには、建物の基礎の段階から検討・工事しなくてはいけないので主に新築で旅人されていますが、リフォームには不向きです。また、ここ数年「制震」という新しい技術が出始めました。
建物に入力される地震力を制震部材で抑制しようという補強方法です。しっかりとした計算に基づいて、制震部材の設置位置、設置量などが決められ、非常に有効な補強方法なのですが、大きな危険もはらんでいます。
新築で「制震」部材を導入しているハウスメーカーなどもありますが、新築の場合は、現在の建築基準法どおり、もしくは、それ以上の性能が確保された上に副賞部材を設置するので、その構造性能は建築基準法が最低限担保してくれます。しかし、リフォーム時には建築基準法どおりに設計されているかという建築確認は必要ないため、その構造面の性能の担保は事業者の技術力に依存することになります。制震部材をリフォームで使用する場合は、「壁の量は現行の基準法どおりに増やして、その上で制震部材を利用しましょう」と言う提案になります。しかし、注意が必要です。
基準法どおりにすれば本当は100の量の壁が必要なのに「この制震部材を設置すれば壁の量が80でよい」という提案が必然的に多くなります。これが危険なのです。しっかりとした計算に基づき性能が発揮されれば問題ないのですが、その技術がない事業者が設計・施工した場合、期待していた耐力100という性能が発揮できず被害を受ける可能性が大きくなるのです。
耐震補強は壁を増やせば基本的な住宅の強さは増大するので、かけたコストに対してその安全性が担保されやすいのですが、制震部材はその事業者の技術力に大きく依存するため、危険側に作用してしまう恐れがあるということなのです。
制震部材を検討するには限界耐力計算という複雑な計算を伴って補強箇所や補強する量などを検討しなくてはならないのですが、多くのリフォーム会社や工務店はこの計算がほとんどできません。設計事務所ですら多くの事務所がこの計算ができないのが実情です。もし制震部材を勧められたのであれば、技術力のある事業者であることをしっかり確認するか、現行の建築基準法で求められている壁の量を満たした上での制震部材による補強をお勤めします。
建築基準法は大きな地震被害を受けるたびに、法律の内容を改正してきています。1978年6月に発生した宮城県神地震の被害を受けて、1981年6月に、木造住宅の壁の量の規定が強化されました。1995年1月に発生した阪神・淡路大貫災ですが、その震災の被害状況を受けて、前述のとおり2000年6月に建築基準法が大きく変わっています。
一つは、壁の配置バランスの問題です。2000年6月よりも前には、建築基準法には「釣り合いよく配置」しなさいとだけ明記されていたため、何をもって釣り合いがよいのか不明だったため、結果的には壁の配置バランスについてはほとんど検討されていませんでした。
もう一つは、木と木を組み合わせる接合部の規定です。2000年6月よりも前には、建築基準法には「くぎその他の金物」で接合すればよいという表現しかなかったため、接合部はくぎで留まっていれば建築基準法違反ではありませんでした。しかし、阪神・淡路大賞災のような大きな地震力を受けると、くぎなどは簡単に外れてしまい、まったく役目を果たさなかったのです。
そこで、接合部の規定が具体的に定められ、特徴的なのがホールダウン金物の使用がほぼ義務づけられたということなのです。機会があったら、近くの新築現場を見に行ってみてください。間違いなくホールダウン金物が取り付けられているはずです。ホールダウン金物とは、基礎のコンクリートから立ち上げたアンカーを住としっかり固定し、地震力で柱が土台から引き抜けてしまうのを基礎のコンクリートの力でしっかり抑え込む金物です。
木造住宅は地震に弱いというイメージがありますが、決して弱くはありません。日本各地に建てられた木造の神社・仏閣が数百年を経ても残存している事実がそのことを物語っています。
地震の振動エネルギーは建物の重力に比例するため、重い建物ほど大きく揺れます。木材は鉄やコンクリートに比べて軽いので、同じ大きさの建物では木造の揺れが一番少ないのです。
しかも、木材は曲げの力にも強いのです。同じ重さでの材料の強さを比較すると、圧縮に対する強さは鉄の約2倍、コンクリートの約9.5倍、引っ張りに対しての強さは鉄の約4倍、コンクリートの225倍もあります。
鉄やコンクリートは、ある一定以上の曲げの力が加わると突然破壊しますが、木材は少々の曲げの力が加わっても耐久性があり、また同じ状態に復元する力があります。地震などの大きな力を受けたときも、ある程度変形しながら力を逃すという性能があるのです。
もう一つは、意外にも火災に強いことです。木材は、表面が炭化すると内部まで燃焼しない性質があり、一定以上の断面を持つ太材は火災に耐えることができます。鉄やアルミニウムは加熱すると3〜5分で強度が著しく低下しますが、木材は15分経っても約60%の強度を維持できると言う見解を持つ人もいるのです。
したがって、このような軽くて強い木材の特性を生かし、耐震性能を十分に考慮して設計・施工した木造住宅であれば、“地震にも強い住宅”といえるのです。
また、木材はコンクリートと違い、呼吸(調湿機能)をしています。夏の多湿時には湿気を吸い、冬の乾燥時には湿気を吐き出します。木は人が快適に過ごせるように、湿度の調節をしているのです。さらに、木は熱を伝えにくい性質があります。本の主成分であるセルロースやリグニンという有機化合物が不良伝導体であるうえに、 細胞と細胞の間に蓄えられた空気が断熱効果をもたらします。
Copyright © 一級建築士事務所 株式会社OKUTA All Rights Reserved.